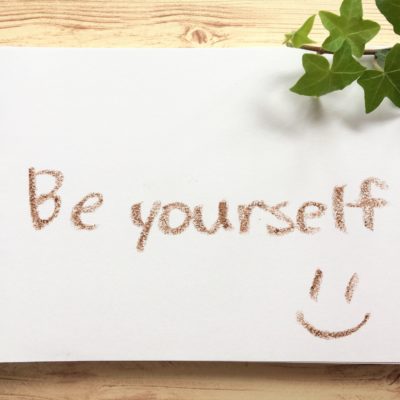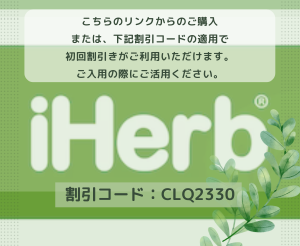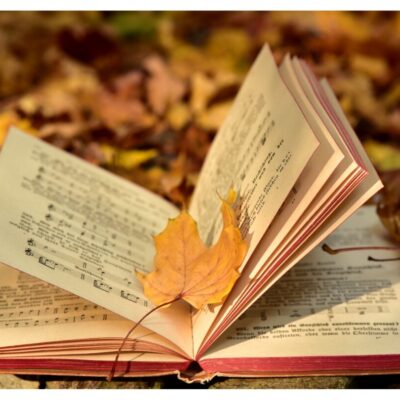自身の発達障害を疑って検査を受けたお話は以前ブログに書いたのですが、今回はそもそも発達障害とはどういったものなのかということについて 、感じたことや、調べたこと、体験したことなどを含めてまとめてみようと思います。個人的主観が多々ですので、ご了承くださいませ。

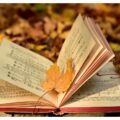
そもそも発達障害とは、生まれ持った脳の特性とも言えるようなものなので、例え私のように大人になってから診断された場合であっても、その症状や特徴が大人になってから突然現れるとういうものではなく、幼少期(生まれた時)からずっとあるもので、これからもずっとあるものです。
また、だとしたら、現在それによって生じている(かもしれない)問題や生きづらさをどう治していくかを考えるよりも、それらとどう付き合っていくかということを考えていくほうが合っているように感じます。
子供の頃に診断された場合には、学校やその他の施設などでサポートを受けることも可能かもしれませんが、大人になるまでそういった機会がなかった場合は、発達障害者としての問題に直面しつつも、何かしら他の部分で補ったり学んだりしながら本人が頑張って生きてきたのではないかと、小さな頃の私を思い出しては思ったりもします。
大人の発達障害という言葉をよく聞くようになってきたなぁと感じる(個人的感覚)昨今ですが、その言葉を聞くたびに、子供の頃には気づかれなかったりスルーされていた私のような方々が沢山いらっしゃるのかもしれないと思うようにもなりました。
私が小さかった頃は、大抵のできないことは、根性が足りない、努力が足りないと大人に言われていたので、私自身、何かできないことがあった時には、私が不出来だからだと信じて疑いませんでしたし、母も父も、自分の子供が発達障害だと疑うようなこともなかったんだと思います。
また、自分が発達障害だと親にカミングアウトすることで、少なからずショックを受けるであろうことは理解しているのと、そこから派生すると思われるあれやこれやを怒涛のように想像してしまい、未だ親には報告できずにいますが、せっかく(?)、自分が発達障害(ADHD併発のASD)だと分かったことで学べたことも多くあるので、自分で整理する意味も含めてブログとしてまとめておこうと思いました。
目次からお好きな場所をご覧いただけます。長くなりますが、何か少しでも必要な方の参考になれたら嬉しいです。
発達障害の種類と特徴(大きく分けて)
発達障害は、脳の機能に関わる発達の問題が原因となる障害と言われており、個々の発達や行動に影響を与えるさまざまな状態のことを指しています。ここでは、主な発達障害の種類4つの特徴について簡単にあげていこうと思います。
また、いくつかの障害が併発した場合についてと、自閉症がそれ単体としての扱いではなく「スペクトラム」として扱われるようになった経緯について、現在(投稿当時)ASD(自閉症スペクトラム障害)の中に含まれているいくつかの診断名についても少し触れてみます。
ASD: Autism Spectrum Disorder(自閉症スペクトラム障害)
1つ目はASDです。発達障害と聞いて多くの方が思い浮かべるのがこのASDなのではないでしょうか?
ASDの主な特徴の1つとして、社会的なコミュニケーションの困難さが挙げられます。
他者との会話が苦手だったり、相手の気持ちを読み取ることが難しい(理解が及ばない、自分はそう思わない為分からない)というものがあります。
例えば、友達と一緒に遊んでいたとしても突然1人で遊びだしたり、会話をしていてもその流れが理解できず、または頭の中でその会話の話題から派生する考えを展開したその先の話題を口にしてしまい、周りを困惑させてしまうということもあります。
また、興味のある物事については、それについて詳しく知りたいと欲する高い知識欲と好奇心を備えています。例えば、電車好きの発達障害のお子様が、電車の種類や時刻表を暗記しているというケースもあります。
音や光、触感にたいして非常に敏感だったり、逆にとても鈍感だったりという特徴もあります。
敏感な場合には、騒がしい場所では耳を塞ぎたくなったり、特定の素材の衣服が苦手であったりと、自分が望む望まないに関わらず、その感覚に対しての情報量が怒涛のように押し寄せてくることが苦痛や実際の痛みとして感じられる場合もあります。
ADHD(注意欠陥/多動症)
2つ目はADHDです。ASDに次いで発達障害の代名詞的なものになるのかもしれません。
ADHDの主な特徴としては、不注意や多動性、衝動性があげられます。
注意力が散漫だったり、集中することが難しかったりする為、何かをしている時に他のことに気を取られ、そのままそちらの事をしはじめたりする場合もあります。
また、じっとしていることが苦手で、常に体を動かしていたいと感じることが多く、思いついたことを考えるより先に行動に移しがちなので、突発的に危険な状況に陥りやすいという傾向もあります。
学習障害(LD)
3つ目は学習障害です。
学習障害の中には、読字障害(ディスクレシア)、書字障害(ディスグラフィア)、算数障害(ディスカリキュア)が含まれています。
読字障害(ディスクレシア)は、読むことに困難を抱えます。
文字を正しく認識できず読むことに苦労します。例えば、文章を読み上げる時に、文字が逆さまに見えたり、単語を飛ばして読んでしまうことがあります。
書字障害(ディスグラフィア)は、書くことに困難を抱えます。
文字を書くのが苦手で、文字の形を正確に書くことにおける困難を生じます。例えば、書くこと自体に時間がかかる為、手書きの課題に時間がかかったり、頑張って書いてもその文字が認識しずらい形となってしまう場合があります。
算数障害(ディスカリキュア)は、計算することに困難を抱えます。
数字や計算に関する理解に対して難しさを感じます。例えば、単純な足し算や式算だとしても、数字の概念自体の理解に難しさを感じる為、結果として計算ができないということに繋がったりします。
発達性協調運動障害(DCD: Developmental Coordination Disorder)
4つ目は発達性強調運動障害です。
発達性協調運動障害により、運動能力が同世代の子供と比べて著しく遅れていたり、手足を上手く使えない場合があります。
例えば、ボールを投げたりキャッチしたりするのが苦手だったり、手先が不器用で細かい作業が難しかったりします。また、体を使う動作がスムーズではなく、転んだりものにぶつかることが多かったりもします。その為、階段の昇り降りに長い時間が必要だったり、よく物を落としたりします。
発達障害の併発(併存症)について
発達障害は、ひとつの障害だけではなく、複数の障害が同時に存在する場合もあります。
これを「併発」または「併存症」といいます。それぞれの障害の特徴が組み合わさって出てくる場合もあります。
例えば、私のようにASDとADHDを同時に持つ場合は、社会的なコミュニケーションが苦手であり、同時に注意力が散漫で衝動的な行動と受け取られるような言動をしがちです。
以下に併発した場合の例をいくつかあげてみます。
ASDとADHDの併発
社会的なやり取りが難しく、同時に多動性があり落ち着きがないことにより、集団活動で困難を感じる場合が多いです。集団行動が必要な場面で、口に出さなくていいことを口にしてしまったり、自分なりの判断で単独行動に出たりします。結果的にそういったストレスを避けるために社会的関わりを遠ざける傾向が強くなりがちです。
LDとADHDの併発
読み書きや計算が苦手である一方、集中力が続かない為、学習において大きな困難を感じることがあります。同時に複数の仕事を短時間で処理したり、大量の情報を一気に理解して動く仕事などは、とてもストレスがかかる場合が多いです。
ASDとLDの併発
社会的なコミュニケーションの難しさと学習障害が同時に存在する場合、周囲との交流に困難を感じる傾向が強くなります。社会的な関わりが必要となる場面において、その場の空気を上手く読めないことと、短時間での読み書き計算による情報処理の必要性から大きなストレスに繋がることが多いです。
自閉症がスペクトラムとして扱われるようになった経緯
さて、自閉症はもともと、個別の診断カテゴリーとして扱われていたようですが、その後の研究によってその症状は様々な形で現れることが分かり、『スペクトラム』という概念が導入されるようになりました。
自閉症が『スペクトラム』として扱われるようになった背景には、長年の研究と診断の進化による影響が大きいようです。
自閉症という概念事態は、1943年にアメリカの精神科医 レオ・カナーによって記述されました。
彼は、自閉症を持つ子供たちが社会的な相互作用に重大な困難を持つことに着目して、『早期幼児自閉症(Ingantile Autism)』として定義していて、当時の診断では、主に重度の社会的、コミュニケーション的な困難を持つ子供たちに限られていたものだったようです。
その後、イギリスの研究者 ハンス・アスペルガーが、カナーの定義したものよりも軽度の自閉症に似た特性を持つ子供たちを『アスペルガー症候群』として記述しました。アスペルガー症候群の子供たちは、言語の遅れがなく、知的障害も伴わない一方で、社会的なコミュニケーションに困難を抱えていました。
このような経緯の中で、自閉症は重度から軽度までさまざまな形で現れることが認識され始めたことで、診断基準の範囲が徐々に広がっていきました。
1990年代から2000年代にかけて、自閉症に関する研究が進む中で、自閉症の統制が非常に多様であることが明らかになってきました。重度の自閉症からアスペルガー症候群、高機能自閉症と呼ばれる知的障害を伴わない軽度の自閉症まで、様々な症状の組み合わせが存在することが分かってきました。
このような多様な特性を包括的に理解するために『スペクトラム』という概念が導入されることになったようです。これによって自閉症が1つの固定された障害というよりも、症状の程度や現れ方が様々な濃さを持つものであることが強調される形となりました。
2013年に、アメリカの精神医学会が発行する「精神障害の診断と統計マニュアル(DSM)」の第5版(DSM-5)で、正式に『自閉症スペクトラム障害』という名称が採用されたことにより、それまで個別の診断として扱われていたアスペルガー症候群や広汎性発達障害などが、すべて『自閉症スペクトラム障害』という1つの診断として統合されました。
上記のような経緯によって、『自閉症スペクトラム障害』というカテゴリーができました。
以下に、自閉症スペクトラム障害の中に含まれる診断名とその特徴をあげていきます。
『自閉症スペクトラム障害』の中に含まれる診断名とその特徴
自閉症スペクトラム障害(ASD)という名称の中には、少し前までは以下のような診断名がついていたものが含まれています。
自閉症(Autism)
社会的相互作用やコミュニケーションにおける困難が顕著にみられます。また、興味の範囲が偏っていたり同じ行動を繰り返す特性を持ちます。症状としては重度から軽度まで様々となり、知的障害を伴う場合も多くあります。
アスペルガー症候群(Asperger Syndrome)
言語や知的発達における遅れはないものの、社会的なコミュニケーションに困難を抱えることが多い傾向にあります。特定の興味に強く没頭する傾向が顕著です。DSM-5では、自閉症スペクトラム障害の一部とされて、個別の診断名としては使われなくなりました。
広汎性発達障害 – 特定不能(PDD-NOS: Pervasive Developmental Disorder-Not Otherwise Specified)
自閉症やアスペルガー症候群の診断基準には完全に当てはまらないものの、いくつかの自閉症的特徴を持つ状態。DSM-5では、PDD-NOSもASDとして統合されました。
小児期崩壊性障害(Childhood Disintegrative Disorder)
正常に発達したあと、2歳から4歳ごろにかけて急激にコミュニケーションスキルを含む社会的なスキルが顕著に落ちてしまう稀な障害。小児期崩壊性障害についても、ASDの一部として見なされるようになりました。
番外編
一時期は自閉症スペクトラム障害の一部として、レット症候群(Rett Syndrome)という障害も含まれていたようです。
レット症候群は、主に女児に見られる神経発達障害で、典型的には生後半年から1歳半頃まで正常に発達した後、突然発達の停滞や後退がおこります。症状としては、言語能力や運動機能の喪失、手を揉んだり手を洗ったりするような手の繰り返し運動、重度の知的障害、運動の協調性の揉んだんや発作などが含まれます。
レット症候群の原因は主に、X染色体上の遺伝子の変異によるもので、この遺伝子の変異が脳の発達に重大な影響を与えることによるようです。その為、他の発達障害とは異なり、明確な遺伝的原因を持つ特定の疾患として分類されるようになりました。
自閉症スペクトラム障害(ASD)は、特定の遺伝的原因が判明していないことが多く、その症状も多様です。
ASDは主に社会的コミュニケーションの障害と、興味や行動の制限と反復が特徴的ですが、レット症候群は進行性の疾患であり、特定の遺伝子変異に基づく神経変性疾患とされています。また、ASDは多くの症状が幼少期から持続的に現れるのに対し、レット症候群は一度発達が停滞・後退し、その後の進行は予測可能な経過をたどっていきます。
このような理由から、レット症候群は現在、自閉症スペクトラム障害の中には含まれず、独立した疾患として分類されています。
発達障害は、例え同じ診断名だとしても、個々に異なる特性となっているため、この診断名ならこの対策という一辺倒のものではなく、それぞれの特徴に応じた対応や対策が必要になってきます。また、障害が複数併発することで、困難さが更に生じたりもします。
大人の発達障害の診断方法とは
社会人になってから自身の発達障害を疑って病院に行くというのは、結構ハードルが高いものに感じますし、何をするか不安になったりもすると思います。
発達障害の診断をする為のテストの種類や数などは、先生によって若干違うこともあるようですが、ここでは、大人になってから発達障害を疑う場合の手順や診断方法の1つの例として、私が受けたものと調べたものをまとめた形で書いてみたいと思います。
事前に流れが少しでも分かってる方が安心できる部分が増えるのではないかと思いますので(私はそういうタイプです。むしろ流れが分からないとパニックになりがちです。)ご参考までに。
1 初回受診
精神科医や臨床心理士、発達障害専門医などに相談します。自身の発達障害を疑って受診した場合は、以下のような内容についてヒアリングが行われます。
- 子供の頃から現在までの生活や行動パターンについて。例えば、学校生活、仕事、社会で人との関わり方、家庭生活における困難さ、どのような場面で困難を感じるのか、気になる症状があればその具体的な内容(社会的なコミュニケーションの困難さや注意力の散漫さ、反復行動など)について。
- 発達障害は遺伝的な要因が関与する場合も多い為、家族に同様の症状を持つ人がいるかどうか。
2 専門家による観察や行動評価
診断を行うにあたって、医師や心理士による行動や言動における、以下のような評価が行われます。
- 患者がどのように対話し、どのように非言語的なコミュニケーションを行っているかの観察。アイコンタクトやジェスチャー、声のトーンなどがここに含まれます。
- 感覚に対する過敏性や鈍感さがあるかどうかの確認。騒音や、明るい光、特定の食感に対する反応などがここに含まれます。
3 心理検査と診断ツールの使用(テスト)
心理検査や診断ツールを使って、発達障害の特性を評価します。一般的に使用される診断ツールとしては以下があります。
WAISーIV(ウェクスラー成人知能検査)
知能検査の一種で、知的な能力の偏りや、特定の認知機能における困難さを評価します。
こちらのテストは1人で回答するものではなく、心理士さんと一緒に時間をとって実施する検査となります。
以前私がWAIS-IVを受けた時のブログでもその内容について触れています。
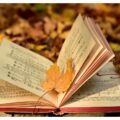
AQ(自閉症スペクトラム指数)
大人の自閉症スペクトラム傾向を測定するための質問表です。質問に対して自己評価を行い、その点数によってASDの特徴があるかどうかの評価をします。
CAARS(Conners’ Adult ADHD Rating Scales)
大人のADHDの傾向を測定するための質問表です。質問に対して自己評価をおこなう「自己記入式」と、家族、友人、同僚など、最近の対象者をよく知る人が評価をする「観察者評価式」があります。
4 診断の確定
前述したようなステップを踏みながら情報を集めて、専門の医師がそれらを総合的に分析・判断した上で診断名が確定されます。
知能テストをした場合には検査結果として心理士さんからのフィードバックはありますが、心理士さんは発達障害の『診断』はできないので、そのテストの結果も含めて総合的に判断して、診断は専門の医師(担当医)が行います。
ここでいうフィードバックとは、知能テストの結果から推測される生きづらさやそれに対してどう対処していくといいかなども含まれています。
私の場合は口頭でのフィードバックだけでなく後から見返したりもしたかった為、有料にはなりましたが紙でも結果をいただくことにしました。今でも時々見返してはそうだったそうだったと冷静に自分のことを確認できるので、私にとってはとても良いなと思います。
発達障害の診断後は、生活の質を向上させるため、必要に応じてそれぞれのニーズに合わせたサポートや治療が提案、提供されたりもします。
もしかすると、自分が想定していたような診断がされない場合もあるかもしれませんが、少なくとも、診断のための作業を通して自分の特性を理解したり明確化することは、自分の人生の戦略を立てやすくなることに繋がるのではないかと感じました。
また、どうしても診断結果に納得がいかない場合などは、セカンドオピニオンとして他の先生に相談してみるという選択肢もあると思います。
その場合は最初に受診した医療機関からの同意を得て紹介状や検査結果などを受け取って行くというステップになるようです。
他の先生に相談する前に、なぜ診断結果について納得がいかないのかなどを予め紙に書いて整理しておくといいかもしれません。
発達障害の誤診されやすい障害や二次障害について
※ 再度のお断りとなってしまいますが、ここに書かれていることは何かのヒントにはなれど、自分や誰かを診断する為のものではなく、こういうこともあるよという、1つの情報としてシェアするものとなります。そして個人的主観です。
最終的な判断(診断)については、専門の医師のみができるものですので、必要な場合には専門家にご相談することをお勧めいたします。
・・・
誤診と言うと聞こえが悪いとは思うのですが、大人の発達障害の方が、発達障害ではなく他の診断名として診断されることはあるようです。
それを誤診と呼ぶのかどうかという点については色々と考える所はありますが、他に適切な表現が思いつかないので、ここでは誤診という言葉を使わせていただこうと思います。
以下に、発達障害と誤診されやすい診断名と、併存する可能性のある診断名(二次障害)を考えられる理由と一緒にあげていきます。
誤診されやすい診断名の例
うつ病(抑うつ障害)
発達障害のある方は、社会的な孤独感や日常生活でのストレスが多いことからうつ病を併発しやすい傾向にあるようです。
発達障害の特徴が見過ごされたまま、気分の落ち込みや疲労感などが目立つ場合などに、うつ病と診断されやすくなるようです。また、自己評価の低さや絶望感が強調されている場合などは、発達障害の症状がその背景に隠れてしまう場合もあります。
不安障害
社会的な不安や強い緊張感というのは、発達障害の方によくみられる症状の1つとしてあげられます。
ただ、発達障害に起因する社会的なコミュニケーションの困難さが、不安として表れることもあり、そこから不安障害として診断される場合もあるようです。
脅迫性障害(OCD:Obsesive-Compulsive Disoder)
発達障害の方は、反復行動やこだわりを強く持つ場合があるため、これが脅迫性障害としての診断に繋がることもあるようです。
例えば、自閉症スペクトラム障害(ASD)の一部の症状は、強迫行為や儀式的な行動との区別がつきにくいため、OCDとして診断されることもあるようです。
双極性障害
注意欠陥・多動性障害(ADHD)の症状の1つである、衝動性や気分の波が、双極性障害の躁状態や抑うつ状態に似ている為、双極性障害と診断されることもあるようです。
特に、日常生活の中で、ADHDの症状として気分変動を引き起こしている場合にそういった可能性が高くなるようです。
境界性パーソナリティ障害(BPD:Borderline Personality Disorder)
感情の不安定さや対人関係の問題が堅調である場合に、境界性パーソナリティ障害と診断されることがあるようです。
ASDやADHDの方が示す衝動性や感情のコントロールが困難である点において、BPDの症状との区別がつきにくいことが原因のようです。
睡眠障害
発達障害のある方は、不規則な睡眠パターンや睡眠障害を抱えていることが多いため、これが主要な問題としてみられた場合に、睡眠障害として診断されることがあるようです。
実際に、発達障害が原因で不眠や睡眠の質の低下が引き起こされているケースは少なく無いようです。
反抗挑戦性障害(ODD:Oppositional Defiant Disorder)
ADHDの方は、規則や権威に対して反抗的な態度を示す場合があり、そこが強調された場合にODDとして診断されることがあるようです。
感情調整の困難さや衝動性はODDの症状として現れることのあるものですが、実はその根本にはADHDがあるという場合もあるようです。
なぜ誤診が起こるのか?
このような誤診が起こる理由として、発達障害の症状が他の精神疾患の症状ととても似ている場合が多いことがあげられます。
特に、大人になってからの発達障害の診断は、子供の頃の発達歴や社会的機能の低下などを振り返る必要があり、その際に特定の症状だけが強調されると、発達障害の症状がその影に隠れてしまうこともあります。
また、患者自身が発達障害に対する情報をあまり持っていなかったり、患者の親が子供の頃の患者の様子から発達障害の可能性を考えたことがない場合なども、他の診断名が先行することに影響を与えやすくなります。
併存する可能性のある診断名(二次障害)
発達障害の特性は生きづらさに直結している場合も多くありません。
そのような場合に、自分自身でどうにかできれば問題ないのかもしれませんが、そうでなかった場合には、精神的や肉体的に大きな負担やダメージに繋がることも多いようです。
ここでは、発達障害をベースとして精神的や肉体的な負担やダメージを受け続けていた場合に考えられる二次障害、発達障害と併存する可能性のある診断名について、あげてみたいと思います。
そもそも二次障害とは?
二次障害とは、もともとの障害や病気(一時障害)に対して適切な支援や治療がなかった結果として、精神的・身体的な健康問題が新たに生じること、一次障害そのものが直接の原因ではなくて、その影響や社会的な環境、生活の中での困難などが積み重なることで引き起こされる障害や病気のことを指します。
発達障害による二次障害
発達障害の方が適切なサポートの無いまま、社会的な孤独やストレスなどを長期間抱え続けた場合に懸念される二次障害の例として以下のものがあげられます。
うつ病(抑うつ障害)
発達障害の特性が理解されず、学校や職場での失敗や対人関係のトラブルなど、適応が困難な状況が続くことで自己評価が低下し、そういったことにより長期間にわたったストレスや失望感が蓄積することでうつ病の発症に繋がりやすくなります。
うつ病の代表的な症状としては、持続的な気分の落ち込み、無気力、興味の喪失、睡眠障害、食欲不振などがあります。
不安障害
発達障害により、予測できない出来事や社会的な状況に対して大きな心配や不安を感じたり、特定の状況に対しての回避行動やパニック発作がみられる場合があります。対人関係や仕事でのプレッシャーに対応できない場合などに、このような不安障害に繋がる場合があります。
パニック障害
発達障害の方が社会的な孤立感や極度のストレスを感じたり、社会的期待に応えられないプレッシャーから無意識的に逃れようとした結果として、動悸や息切れ、発汗などの身体的な症状を伴う強い不安感に襲われることがあります。また、急激に襲ってくる強い恐怖感や不安感に加えて、息苦しさや胸の痛み、眩暈などの身体症状が現れることもあります。
大人になってから発達障害と診断されるメリットやデメリット
大人になってから自分は発達障害かもしれないと、診断してもらおうと行動する方というのはきっと、今までも、そして今も、毎日の中での困りごとに頭を悩ませている方が多いのではないでしょうか。
かくいう私もそんな1人で、私の魔女の師匠からの助言を受けて重い腰をあげることができました。

ですがもちろん診断されたからといって、症状が軽くなる訳でもコミュニケーション能力が劇的に高くなる訳でもありませんが、不思議なことに自分に診断名がついたことにより、冷静に自分自身を見つめられていい意味で諦められるようになった分、前よりも落ち着きが増えた感覚は少なからずあったりします。
自分は何者なのかとか、こんな自分は本当に大丈夫なんだろいろうかというような宙ぶらりんな心の状態はとても辛いものだと思うのですが、物心ついた時からずっと宙ぶらりんだったので、その辛さはずっとあったにも関わらず、そういった辛さに対する感覚に蓋をしていたのかもしれないと気づいたりもしました。
診断されたことによって、そうかだからかと納得できた分、以前よりも自分の軸が定まったような感覚にすらなったりします。
個人的には、大人になってから発達障害だと診断されたことに大きなメリットを感じています。
デメリットといえば、診断を受けてからすでに1年以上親に言えてなく悶々としていることと、いつまで病院に通わないといけないのかよくわからないことです。
親に言えないのは、うつ病だと診断されていた時にも、何の冗談を言ってるんだと、気合いが足りない、根性だ根性だと薬をやめさせられ(病状が悪化して後から謝罪されました。どなた様も薬を突然止めるのはおすすめしません。)たので、また今回も冗談だろと笑われるのが怖いのと、うちの親は、発達障害は子供の体に良くないものばかり食べさせるからなるものだと言っていたのを覚えているからです。
前述した通り発達障害は脳の使い方の違いによるもので、大きくなってから診断されたとしても、それ自体は子供の頃(生まれた時)からあるものだと言われています。
多分私がカミングアウトした場合でも、食べ物が。。。と言われると想像できますので、その際には説明をする必要があると思うのですが、説明してもバカにされるか、信じてもらえないか、自分の育て方が悪いと言ってるのかと逆に怒られるんだろうなと思うと怖くて、言えません。
そのうち機会があれば、言ってみようかとは思います。(その場合はブログに書こうと思います。)
また、私は以前大量に向精神薬を処方されていて、それに助けられていた部分も多々あるのですが、私が私ではない感覚が常にあったので、今では出来るだけ薬は飲みたくない派になっています。
ですがやはり調子が悪い時などには、先生から精神薬を処方されますし、飲みたくないと言っても、飲んで良くなった人もいる、めちゃめちゃ少ない量だから試してみてと勧められます。
自分でももっと気楽に試してみればいいとは思いますし、出される薬も以前頓服として飲んでいたもので特に大きな問題もないことは分かるのですが、なぜか体が飲むのを拒みます。
毎回『今回も薬を飲めなかった』と先生に伝えるのはしんどいですし、飲めばいいし嘘をついてもいいのに、それもできないのでやっぱりしんどいです。
なのでとにかく大事なのは、発達障害は調子のいい時はあっても、治るというものではないということを頭におきながら、自分がどんな状態を望んでいるのか、そしてその為には何ができるのか、何が必要なのかをその都度考えるようにしています。
以下に、大人になってから発達障害と診断されることのメリットとデメリットを3つずつあげてみようと思います。
メリット3つ
自己理解が深まる
ずっと『なぜ自分は他の人と同じようにできないのか』と悶々としていた感覚が、発達障害の診断を受けることで、生まれつきの脳の特性によるものであることや、よく分からなかった自分の行動や思考パターンへの理解に繋がることは多いのではないかと思います。
今までの『できない』が、単なる怠惰や能力不足によるものなどではなく、特性によるものだと分かることによって、自己否定や無力感が和らいだり、自己肯定感が高まることもあると思います。
適切な支援や治療に繋がりやすくなる
発達障害が診断されることで、医療機関や支援機関などのサポートにつながりやすくなります。
また、職場などにおいても理解を得やすくなったり、環境を整えるための配慮が受けやすくなる場合もあります。
新たな視点で人生を見直す機会になる
診断後、自分の強みや弱みについて考えて再評価をすることで、適切なキャリアや生活スタイルの方向性が見えてきたり、より自分らしく充実した人生を送るためにどうしたらいいかという選択肢が見つかりやすくなると思います。
自分の特性に合った生き方や仕事を選びやすくなったり、対人関係のストレスが少ない職場や自分のペースで働ける環境を選ぶことで、仕事の満足度や生活の質が向上する場合もあります。
デメリット3つ
社会的なスティグマや誤解
発達障害に対する理解が十分では無い社会では、発達障害と診断されていることに対する偏見や誤解を受ける可能性はあります。これが職場や家庭での人間関係に影響を及ぼすような場合には、不当な扱いに繋がる場合もあります。
心理的なショックや不安
大人になってからの診断は、自分の人生観や価値観を大きく揺るがすことも考えられます。診断されたことにより、自分のアイデンティティが揺らいだり、過去の経験や人間関係を見直さざるを得なくなったりして、日常生活における混乱や不安に繋がる場合もあります。
対応に時間と労力がかかる
発達障害と診断されたあとに、適切な支援を受けるためには、多くの時間と労力がかかる場合もあります。診断を受けるまでに多くの専門家を訪問しなければならない場合や、支援が必要な場合には、経済的な負担も増えたりもします。
大人になってから発達障害と診断されることのメリットとしては、自己理解が深まったり、適切な支援が受けられるなどがありますが、同時に社会的なスティグマや心理的ショック、また支援を受けようとした場合でも手続きに伴う負担といったデメリットなどもやはり存在します。
また、子育て中の母親が大人になってから発達障害と診断される場合には、自分の育児能力に対する不安や子供への悪影響を与えていないかという不安が生じる可能性もあります。
同じように、子どもへの遺伝の可能性についてや、子どもも同じように困難を経験するのではないかという不安を感じるかもしれません。
更にはパートナーがその診断をどのように受け入れるかや、家庭内での役割分担にどのような変化が必要かなどの懸念が生まれるかもしれません。
総じて一概に診断されることが良い悪いとは言えないものではありますが、大人になってから診断を受けたいと思い、その為に動けるというのであれば、自分の中で診断されることが何かしらの良い影響を与えると考えている場合が多いのではないかと思います。
診断されることでショックを受けることも、新たな問題が浮き上がってくることもあると思いますが、少なくとも私は、とても納得できたのでスッキリした部分が多いです。
もしも診断された方がいいのかどうかと迷われている方がいらっしゃれば、メリットとデメリット、両方ありつつも、自分はどちらに重きを置くのかというのを考えてみるといいかもしれません。
人にはそれぞれ事情がありますし、環境や状況もそれぞれに色々と違ったりもします。
自分にとってベストな方法を見つけていけるといいですよね。
まとめ
昔の私は、発達障害という言葉を聞いても、自分とは無縁のものと思っていました。
周りの音が気になりすぎるのも、光が眩しくて頭が痛くなるのも、話をしたくても何をどう言えばいいのかと固まってしまって声をかけられないことも、全部全部、ただ私が弱くて不出来だからだと信じていました。
ですが、数十年経った今診断を受けて、やっと、これは脳の使い方が違うから仕方ないんだと思えるようになりました。
自分は発達障害なんだと分かった時に、安心感と一緒にショックも受けましたが、それでも私はこの歳になってからでも、自分が発達障害だと分かって良かったと感じています。
治るものではないので、これからもずっと付き合っていくことになりますが、発達障害だと分かってるのといないのとではきっと、私の心の晴れやかさや軸の在り方が全然違います。
発達障害な私を、ありのままの私を、もっと楽しめたらいいなと思います。
このブログが必要な方に届きますように。
そして少しでも生きづらさへの対処法が増えますように。